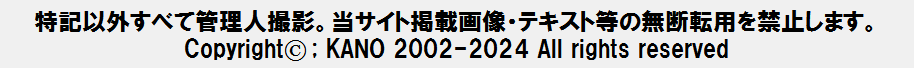|
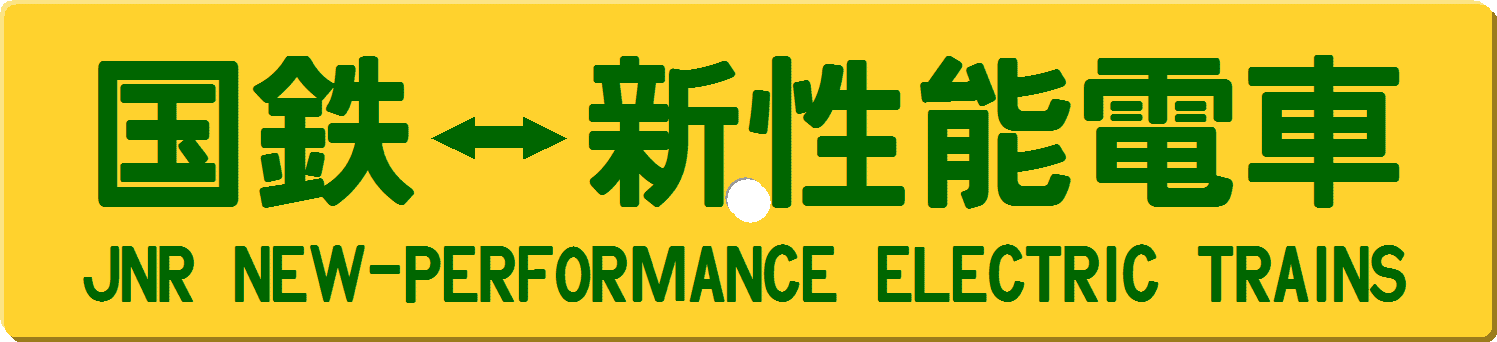 |
| 103�n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �N���n103 1-155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.28-2 1983�N12��27�� �N���n103�� 6�� ��a�� �R���k���I�� |
�V����/�� �N���n103+���n102+�T�n103 +���n103+���n102+�N�n103 �a�̎R �R���k�̓����䂭103�n�C�N���n103�擪��6�A�B�N���n103�͊��������d���ԂŁC1964-1967�N��1-133�C1967-1970�N��134-155���V������܂����B (2015/01/11�lj��@2018/09/23���C�h��) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.38-29 1984�N3��27�� �N���n103�� 5�� �� ���C���{���@���m�{������ |
<��>�N���n103+���n102+���n103+���n102+�N�n103-500�ԑ�<��> ���C���𐼉����鏼�ˋ��103�n5���Ґ��C��ǂ��ʐ^�B105�n�ւ̉�����ԂƂ��ẲȂ̂���ΐ��ւ̓]���ɔ��������Ȃ̂��s���ł��B (2023/04/09�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.N8501-15 1985�N3��23�� F3�Ґ� �N���n103 �� 10�� ���� �����{���@���É� ���Ð�/�� �N���n103+���n102+�T�n103+���n103+���n102+�N�n103+�N���n103+���n102+�T�n103+�N�n103 ���É� ���É��w�ɒ�Ԓ���103�n�����������ʗ�� (2023/05/08�lj�) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.125-28 1986�N4��7�� ��c�k 405F�Ґ� �N���n103-12�� 6�� ���t���@��t�` |
��t�`/�� �N���n103-12+���n102-85 +�T�n103-136+���n103-645+���n102-801+�N�n103-414 ���D�� �J�ƊԂ��Ȃ���t�`�w�ɓ�������103�n�C����3�Ԑ��͌��ݒ��ł��B���̔N3��3���ɐ��D��-��t�`�Ԃ����q�c�Ƃ��J�n�C�ԗ���n�Ƃ��ĒÓc���d�ԋ�V�K�u��h�o���������܂����B�����̐�c�k405F�Ґ���4+6��10���Ґ��Ő�t�`���̓N�n103-413�̂͂��ł����C���̎ʐ^�ł̓p���^�������Ă���C�z�[���ɂ��]�T������̂Ŋ�{6���Ґ��̃N���n103-12�Ǝv���܂��B���t���͂��̂���1988�N12��1���ɐ�t�`-�h��Ԃ��J�ƁC�ԗ���n��1990�N3��1���ɋ��t�d�ԋ�ƂȂ�܂����B�܂��C��t�`�w��1992�N3��14���ɐ�t�݂ȂƂɉ��̂��Ă��܂��B (2015/01/17�lj��@2023/04/08���C�h��) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.130-28 1986�N7��30�� �N���n103�� 6�� ���{�� �͓����と����c ����/�� �N���n103+���n102+�T�n103 +���n103+���n102+�N�n103 �ޗ� ���{���Ŋ���103�n���F�Ґ��B�O5�����I�����W�o�[�~���I���C�Ō���̃N�n103�̂݃E�O�C�X�F�C���̎���܂��܂����[�ł��B (2015/01/17�lj� 2023/04/08���C�h��) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.130-29 1986�N7��30�� �N���n103�� 6�� ���{�� �͓����と����c ����/�� �N���n103+���n102+�T�n103 +���n103+���n102+�N�n103 �ޗ� ���{���ޗ�-�����Ԃ̉����^�p�ɂŊ�����[�X�J�C�u���[��103�n�B (2015/01/17�lj� 2023/04/08���C�h��) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.200-21 1991�N1��15�� ���}�g �N���n103�� 10�� ���c���@�؉������� |
���c/�� �N���n103+���n102+�T�n103+�T�n103+���n103+���n102 +�T�n103+���n103+���n102+�N�n103 ��� ���c���𑖍s����G�������h�O���[����103�n10���B�擪�̃N���n103����9���ڂ܂�AU75�C�Ō���̃N�n103�̂�AU712��2��ڂ��Ă��܂��B�N���n103������ɘA������10���ђʕҐ��͑g�ݑւ����Đ������炵�C���̌�N���n103��5���Ґ��݂̂ɂȂ�܂����B (2022/06/19�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.365-13 1997�N3��27�� �{�q�l H414�Ґ� �N���n103-127�� 4�� ��a���@�� |
�V����/�� �N���n103-127+���n102-273 +�T�n103-284+�N�n103-598 �a�̎R ������s���̑�q�l����4�A�C��O�̓N���n103-127�ł��B�V�[���h�r�[��2�����C����C��H�S���Ǝ肪�����Ă��܂����C�ˑܑ��͌��݁B (2013/02/13�lj��@2023/04/08���C�h��) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �N���n102-1201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.254-37 1992�N1��19�� ���}�g 31�Ґ� �N���n102-1201�� 5�� ���c�� ���H���������� |
���c/�� �N�n103-1201+���n103-1201+���n102-1201+���n103-1203+�N���n102-1201
�䑷�q 103�n1200�ԑ�͉c�c�n���S������������p�ɐ������ꂽ�ԑ�敪�ŁC�O�ʊђʌ`�̓����͐��c���p��1000�ԑ�ԂƓ��l�ł���WS-ATC�𓋍ڂ��Ă���C���������ɃN���n102��z�u����6M1T��7���Ŋ��܂�����1991�N����2�Ґ���4M1T�Ɍ��Ԃ����։���/���c���̕t���Ґ��ɓ]�p����܂����B���̕Ґ��̐擪�Ԃ��N�n103-1201�ł��B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���n102 488-899, 2001-2043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_150505-763 2015�N5��5�� R1�Ґ� ���n102-545�� 6�� �R�z�{���a�c���x���@���� |
����/�� �N�n103-247+���n103-389+���n102-545 +���n103-397+���n102-553+ �N�n103-254 �a�c�� �_�ˎs���Ȃ̂��H�Ƌ^�����炢��q���قڂ��Ȃ��x���̕��ɉw�a�c�����z�[���ł����B���n102 487-899, 2001-2043�͗�[�W��������1973�N����1981�N�ɑ������ꂽ�O���[�v�ŁC�ʐ^�̃��n102-545��AU75A�𓋍ڂ��ė������Ă��܂��B���̕Ґ���2023�N3��18��������207�n�ւ̒u�����������B���N����ꂳ�܂ł����B (2023/03/16�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �N�n103 1-179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.27-11 1983�N12��27�� �N�n103-15�� 8�� ��a���@�R���k���I�� |
�V����/�� �N�n103-15+���n103-15+���n102-15+�T�n103-80 +�T�n103-361+���n103-16+���n102-16+�N�n103-16 �a�̎R ���̓��̎R���k�͔���̐��E�ł����B���܂��B�e�ɍs�������ɂ��ː���Q�ō�a���������������ƂȂ��Ă��܂��܂����B4M4T��8���ђʕҐ��ł��B (2023/04/13�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.27-14 1983�N12��27�� �N�n103-16�� 8�� ��a���@�R���k���I�� |
�V����/�� �N�n103-15+���n103-15+���n102-15+�T�n103-80 +�T�n103-361+���n103-16+���n102-16+�N�n103-16 �a�̎R ��Ń_���[�W�����ː���|�̒�q���g���ďC�����B������d�ԋ�(�V�q�l)�̃N�n103-16��1964�N9���ɐ�������r�ܓd�ԋ�(�k�C�P)�ɔz���C1974�N2���ɖP�d�ԋ�(�V�I�g)�ɓ]���C1978�N10���ɖP�d�ԋ������x�悪������d�ԋ�(�V�q�l)�Ɋi�グ�ɂȂ��Ă��܂��B (2023/04/13�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.27-33 1983�N12��27�� �N�n103�� 6�� ��a���@�R���k���I�� |
�V����/�� �N���n103+���n102+�T�n103 +���n103+���n102+�N�n103 �a�̎R ��a���̕��ʂ�103�n6�A4M2T�ŎR���k���z���Ă��܂����B��̎ʐ^�Ɠ������B�_�C�����I���啝�ɗ���܂����B (2015/01/11�lj��@2023/04/08���C�h��) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.33-34 1984�N2��19�� �� 103�n7�� ���� �E EF58 94 �P2030�� ���C���{���@���������m�{ |
���s/�� �N�n103+���n103+���n102+�T�n103 +���n103+���n102+�N�n103 ������ �S�n�`�ɔ�����I�[�����[�̒�^103�n7�A�B�t�B�������M�d�Ȏ��ゾ��������103�n�P�Ƃ̎ʐ^�͂قƂ�ǂ���܂���B (2015/01/11�lj��@2023/04/08���C�h��) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.N8501-16 1985�N3��23�� F14�Ґ� �N�n103 �� 10�� ���� �����{���@���É� |
���Ð�/�� �N���n103+���n102+�T�n103+���n103+���n102+�N�n103 +�N���n103+���n102+�T�n103+�N�n103 ���É� �E�O�C�X�F(����6��)��103�nF14�Ґ��B���m�ȂɃ��C�p�[�����݂���Ă��܂��B�s��\���ɂ͑��ʂɃT�{�����t���Ă��萳�ʂ̕\���͒������Ƃ���Ă��܂��B (2023/05/08�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.128-9 1986�N6��1�� �N�n103�� 4�� �~���@���m�� |
����/�� �N�n103+���n102+���n103+�N�n103 �~ 201�n���ʉ����V�h�s���������܂ƌ�������~���������s��103�n4�A (2015/01/17�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.188-04 1990�N5��5�� �N�n103�� �����@�� |
�В��w�̗��u���ɏ����`�N�n103�C2�Ԑ��ɂ͍��^�]��̃N�n103���Ō���ɂ�������R��s������Ԓ��B (2023/05/18�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.212-22 1991�N4��6�� ��~�m 4�Ґ� �N�n103-100�� 4�� ��ΐ��@�����C�݁����钬 |
�Ί�/�� �N���n103-29+���n102-116+�T�n103-75+�N�n103-100 ��� ��22���F��103�n��~�m4�Ґ���4���ʼn^�]�����Ί��s�������B��O�̃N�n103-100��1967�N3���ɐ����C��V�i�C��J�}�ŋ��l���k���n���Ŋ�����C1979�N3���ɐ僊�n�Ɉړ���JR�Ɍp������܂����B1991�N3������͐�~�m�ɓ]�����C1992�N12���ɔp�ԂƂȂ�܂����B (2022/06/09�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D200_080826-10 2008�N8��26�� H17�Ґ� �N�n103-30�� 4�� �R�z�{���@���R |
�a�C/�� �N�n103-29+���n103-310+���n102-466+�N�n103-30 �O�� ��q�l�̃N�n103-30���܂�2M2T��4�A�C2008�N3�����牪�R�d�ԋ�ɑ݂��o����C�R�z�{�����R�n�惍�[�J���^�p�Ŏg���܂����B �i2023/04/08�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D200_080826-13 2008�N8��26�� H17�Ґ� �N�n103-29�� 4�� �R�z�{���@���R |
�a�C/�� �N�n103-29+���n103-310+���n102-466+�N�n103-30 �O�� ��Ɠ�����q�l��103�n4�A�CH17�Ґ��Ƃ���2008�N3�����牪�R�d�ԋ�ɑ݂��o����R�z�{���a�C-���R-�O���ԁC�ԕ���d�B�ԕ�-���R�ԁC����щF������R-�F��Ԃʼn^�p����܂������C2009�N11���ɔp�ԂƂȂ�܂����B �i2023/04/08���C�h��) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_180502-082 2018�N5��2�� �N�n103-1 ���s�S�������� ������Ŋ��Ă����N�n103-1�BH�S���������g�ɂȂ�X�J�[�g���t���Ȃǂ��Ȃ�肪�����Ă��܂��B (2018/05/12�lj�)  |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_180502-083 2018�N5��2�� �N�n103-1 ���s�S�������� |
�N�n103-1�ԓ��B�ˑܑ������߂��Ă���̂ŃI���W�i���ƕ��͋C���قȂ�܂��B (2018/05/12�lj�)  |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_180502-225 2018�N5��2�� �N�n103-1 ���s�S�������� |
���S�t�H���g�ƃh�A�R�b�N (2018/05/12�lj�)  |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D850_221228-019 2022�N12��28�� �N�n103-1 ���s�S�������� |
��ʑ����猩�����ʁB�Ȗʂɂ��������ƌˑܑ��͖��߂��Ă��܂��B (2023/04/12�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �N�n103 180-212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.N8210-25 1982�N10��11�� �� 103�n 7�� ���� �E EF5861+14�n ���C���{���@�Z�g���ےÖ{�R |
���s/�� �N�n103+���n103+���n102+�T�n103 +���n103+���n102+�N�n103 ������ ��22����103�n7�A�C1971-1972�N�����Ԃŋ���_�ɍs�������ɖ��Γd�ԋ�ɏW���������ꂽ�O���[�v�ł��B�����̓��j�b�g���ƂȂ�C�O�Ɠ��̓V�[���h�r�[��2���C���[�Ԃł��B (2023/01/28���C�h��) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_121011-128 2014�N10��11�� NS405�Ґ� �N�n103-187�� 4�� �ޗǐ��@���s |
���s/��N�n103-187+���n103-422+���n102-578+�N�n103-186 �ޗ� ���s�Ő܂�Ԃ��ޗǍs���ƂȂ蔭�Ԃ�҂�103�n�̊�����N�n���_�˂������V�[���B���[�Ƃ��ēo�ꂵ���O���[�v�ł�����[���������Ă��܂��B (2014/10/18�lj��@2023/04/08���C�h��) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_180224-071 2018�N2��24�� 11:30 NS405�Ґ� �N�n103-186�� 4�� 630M ���� �ޗǐ��@�F�������@ |
���s/�� �N�n103-187+���n103-422+���n102-578+�N�n103-186 �ޗ� ���s�s�����ʁCNS405�Ґ��B��O�̓N�n103-186�ł��B (2018/11/30�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �N�n103 213-268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_150505-761 2015�N5��5�� R1�Ґ� �N�n103-247�� 6�� �R�z�{���a�c���x���@���� |
����/�� �N�n103-247+���n103-389+���n102-545 +���n103-397+���n102-553+ �N�n103-254 �a�c�� �N�n103-247�B����_�ɍs���Ő̌����ꂽ����������^�X�J�C�u���[�̊�B�N�n103 213-268��1973�N�ɑ������ꂽ�O���[�v�ŗ�[���u�����ŗ������Ă��܂��B�܂��C��ʑ��ʂɍs��\�����ݒu�C�O�ʂ̍s��\������d�����ɕύX����ߑ�I�ȃC���[�W�ɂȂ�܂����B��[���ɂ��O�ʂ̒ʕ����͔p�~����܂����B (2023/03/16�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_150505-771 2015�N5��5�� R1�Ґ� �N�n103-254�� 6�� �R�z�{���a�c���x���@���� |
����/�� �N�n103-247+���n103-389+���n102-545 +���n103-397+���n102-553+ �N�n103-254 �a�c�� GW�𗘗p���Ęa�c������K�˂܂����B���̓��̉^�]�͒��[�Q�����������B17:15���Ԃ̗�Ԃ̏�q�͏��Ȃ��C103�n����������ώ@���邱�Ƃ��ł��܂����B�a�c�������牺�L��4M2T6�A�B (2015/05/24�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_170813-274 2017�N8��13�� NS411�Ґ� �N�n103-252�� 4�� �ޗǐ��@���s |
���s/�� �N�n103-251+���n103-456+���n102-612+�N�n103-252 �ޗ� �ޗǐ�10�Ԑ��ɒ�Ԓ���NS411�Ґ��B���悢��M�d�ɂȂ��Ă��܂����B (2017/08/17�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_180224-076 2018�N2��24�� 11:35 NS409�Ґ� �N�n103-226�� 4�� 1629M ���� �ޗǐ��@�F�������@ |
���s/�� �N�n103-225+���n103-455+���n102-611+�N�n103-226 �ޗ� ��z�s�����ʂɏ[�����ꂽNS409�Ґ��B�擪�̓N�n103-226�ł��B (2018/11/30�lj�)  |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_180224-080 2018�N2��24�� 11:45 NS410�Ґ� �N�n103-230�� 4�� 627M ���� �ޗǐ��@�F�������@ |
���s/�� �N�n103-229+���n103-483+���n102-630+�N�n103-230 �ޗ� �ޗǍs������NS410�Ґ��B�擪�̓N�n103-230�ł��B (2018/11/30�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_180224-089 2018�N2��24�� 12:05 NS411�Ґ� �N�n103-252�� 4�� 1631M ���� �ޗǐ��@�F�������@ |
���s/�� �N�n103-251+���n103-456+���n102-612+�N�n103-252 �ޗ� ��z�s�����ʁCNS411�Ґ��B���̎ʐ^�Ɠ����Ґ��ŁC�擪�̓N�n103-252�ł��B (2018/11/30�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �N�n103 269-499, 701-843, 844��850(��) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.N8203-10A 1982�N3��7�� �N�n103 ���^ 10�� ���l���k���@���� |
��{/�� �N�n103+���n103+���n102+�T�n103+���n103+���n102 +�T�n103+���n103+���n102+�N�n103 ��D �����w4�Ԑ��ɓ�������ɍ��^�]��103�n���l���k����Y�a�s���B�I�o�Ȃ��u���Ă��܂��B (2015/02/01�lj��@2023/04/08���C�h��) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.23-15 1983�N9��24�� �N�n103[840-850��]�� 6�� ���C���{���@��ど�V��� |
���/�� �N�n103[833-843��]+���n103[775-785��]+���n102[2032-2042��] +���n103[776-786��]+���n102[2033-2043��]+�N�n103[840-850��] ��� ���m�R����1981�N�ɕ�˂܂œd���J�Ƃ��J�i���A�F6���Ґ���103�n4M2T�~6�{���V����������܂����B��[�����ŃN�n103�͍��^�]���833-843(�)��840-850(����)�C���n103��775-786�C���n102��2032-2043�̍��v36���ƂȂ��Ă���C�N�n103��0�ԑ�Ō�̃��b�g�ƂȂ�܂����B (2023/04/13�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.128-18 1986�N6��2�� �E��44�Ґ� �N�n103�� 10�� ���l���k���@���l�����_�ސ� |
��{/�� �N�n103+���n103+���n102+�T�n103+���n103+���n102 +�T�n103+���n103+���n102+�N�n103 ��D �L�c�d�ԋ悩��]���̃I�����W�o�[�~���I�����[���Ԏ�3����A���������l���k��103�n���F�Ґ� (2015/01/17�lj��@2023/04/08�V���h�[����) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.145-3 1987�N3��30�� �E��76�Ґ� �N�n103-300�� 10�� ���l���k���@�_�c |
��{/�� �N�n103-299+���n103-444+���n102-600+�T�n103-368 +���n103-181+���n102-336+�T�n103-369 +���n103-446+���n102-602+�N�n103-300 ��D JR�ւ̈ڍs���O�ɂȂ�u1987���悤�Ȃ�JNR�v�}�[�N�����t����103�n�E��76�Ґ��B (2015/01/18�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.145-9 1987�N3��30�� �烉�V306�Ґ� �N�n103-763�� 10�� ���������ɍs�� ���쁩������ |
��t/�� �N�n103-763+���n103-707+���n102-863+�T�n103-468 +���n103-708+���n102-864+�T�n103-469 +���n103-709+���n102-865+�N�n103-780 �O�� �\���C���V�m�ƍ̉Ԃ��炭������̐�ʂ����䂭�K�u��d�ԋ�̊ɍs��103�n�B���F5���F�̕Ґ��̗��[�ɉ���6���̍��^�N�n103�����������F�Ґ��B (2015/01/18�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.145-12 1987�N3��30�� �烉�V326�Ґ� �N�n103�� 10�� ���������ɍs�� ���쁩������ ��t/�� �N�n103+���n103+���n102 +�T�n103+���n103+���n102+�T�n103 +���n103+���n102+�N�n103 �O�� ����������F�Ґ��ł����B3�����ō��S���X�g�Ƃ������ƂŁC���悤�Ȃ���{���L�S���̊Ŕ�t���Ă��܂��B (2023/04/23�lj�) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.252-37 1992�N1��12�� ���}�g 23�Ґ� �N�n103-466�� 5�� ���c�� �؉������� |
���c/�� �N�n103-465+���n103-575+���n102-731+�T�n103-296+�N�n103-466 �䑷�q ���c���̕��ʗ�ԁB���ˎԂ͉䑷�q�������������ƂȂ�܂��B����C������113�n�͉䑷�q����������œ������܂��B (2023/05/19�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.254-17 1992�N1��19�� ���}�g 7�Ґ� �N�n103-274�� 10�� ���c�� ���с����H |
���c/�� �N�n103-273+���n103-749+���n102-2006+�T�n103-298+���n103-275+���n102-430+�T�n103-297+���n103-278+���n102-433+�N�n103-274
��� ���c����10���ŏ����鏼�ˋ��103�n���^�]��Ґ� (2023/05/19�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_120103-301 2012�N1��3�� LA2�Ґ� �N�n103-806�� 8�� ������@�ٓV�� |
�O���/�� �N�n103-838+���n103-528+���n102-684+�T�n103-399 +�T�n103-415+���n103-396+���n102-552+�N�n103-806 ����� 50���N�}�[�N��t����103�n�C�߃���LA2�Ґ��B���^�]��^�C�v�ŁC2000�N�ɑ̎����P40N�H�����{�H����C�ˑܑ��̓P����O�ʑ��̈�̉��C�q�����C�w�b�h���C�g�ȂǂȂǁC�����肪�����Ă��܂��B �i2023/04/08���C�h��) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_120103-310 2012�N1��3�� LA4�Ґ� �N�n103-843�� 8�� ������@�ٓV�� �O���/�� �N�n103-843 +���n103-773+���n102-2030 +�T�n103-400+�T�n103-484x +���n103-774+���n102-2031 +�N�n103-802 ����� �����s����103�n�C�߃���LA4�Ґ��B���^�]��^�C�v�̎ԗ��ŁC�P�����ɉ�������Ă��܂��B�������̘g���������̑������̂ɂȂ��Ă��܂��B �i2023/04/08���C�h��) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D200_150718-220 2010�N5��22�� �N�n103-713 �S�������� ���^�]��C��22���h�F�C103�n�B�擪�Ԃ̑O�����̎ԑ̂����W������Ă��܂��B�ȑO�͕�������̐��D���s���ɂȂ��Ă��܂������C�O�[���E���[����s���ɕύX����Ă��܂��B �i2023/04/08���C�h��) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_150718-222 2015�N7��18�� �N�n103-713 �S�������� |
�S�������فC���[����s����103�n�B�^�]�ȑ� (2015/07/20�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_150718-223 2015�N7��18�� �N�n103-713 �S�������� |
���^�]��d�l�̃N�n103�B�^�p�ԍ��ƕҐ��ԍ��[�B (2015/07/20�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_150718-225 2015�N7��18�� �N�n103-713 �S�������� |
103�n�̎ԓ��B10���Ԃ̕\��������܂��B (2015/07/20�lj��@2023/04/08���C�h��) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_150718-226 2015�N7��18�� �N�n103-713 �S�������� |
��{�����ԗ��Z���^�[(�{�I�I)�̏����\�L�B (2015/07/20�lj��@2023/04/08���C�h��) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_170814-281 2017�N8��14�� NK605 �N�n103-829�� 6�� NK604 �N�n103-825�� 6�� �Ԋ������ԗ��� �{���x�� |
�� NK605 <��>�N�n103-829+���n103-771+���n102-2028 +���n103-482+���n102-638+�N�n103-148<��> �E NK604 <��>�N�n103-825+���n103-765+���n102-2022 +���n103-766+���n102-2023+�N�n103-832<��> ��a���Ŋ����߃q�l��103�n6�A2�{���{���ɑa�J�C����12�n�ɂ�14�n�Ȃɂ킪�A������Ă��܂��B (2017/08/17�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_170814-289 2017�N8��14�� NK608�Ґ� �N�n103-844�� 6�� �Ԋ������ԗ��� �{���x�� |
NK608 <��>�N�n103-844+���n103-779+���n102-2036 +���n103-386+���n102-542+�N�n103-244<��> ��������a�J���u����Ă���X�J�C�u���[���^�]��̋߃q�l�U�A�B���̔N��11���ɔp�ԂɂȂ��Ă��܂��B (2017/08/17�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_170814-299 2017�N8��14�� NK608�Ґ� �N�n103-844�� �Ԋ������ԗ��� �{���x�� |
������N�n103-844��1�ʑ��B�ˑܑ������߂��201�n�ɋ߂���ۂɂȂ��Ă��܂��B (2023/04/10�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �N�n103 501-638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.38-28 1984�N3��27�� �N�n103-500�ԑ䑼 5�� �� ���C���{���@���m�{������ |
<��>�N���n103+���n102+���n103+���n102+�N�n103-500�ԑ�<��> �N�n103�`500�ԑ�Ԃ�擪�ɂ����C��֥���c���p�̃G�������h�O���[���F103�n5���̉����C���𐼉��B�擪�̃N�n103�̂ݗ�[�ԂŌ��4���͔��[�Ԃł��B�N�n103�`500�ԑ�͋�����������ԂŃN���n103�̑Ƃ��Đ�������܂����B���������ɌŒ�̂��ߐ��ʉ^�]�ȉ��̃W�����p��[�߂��ȗ�����Ă���O�Ϗ�̓����ƂȂ��Ă��܂��B�����͔��[�œo�ꂵ�C��ɗ�[����������Ă��܂��B (2015/01/11�lj��@2023/04/08�V���h�[����) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.193-01 1990�N7��27�� H408�Ґ� �N�n103-545�� 3�� ��a���H�ߎx���@�P |
�P/�� �N���n103-77+���n102-186+�N�n103-545 ���H�� 1989�N10��20�����烏���}�������ꂽ�H�ߎx���̏��Ԃ����ɎB����103�n�B�H�ߎx���ɂ�1987�N����123�n2������������Ă��胉�b�V�����ɂ̓N�n103-194������3���ʼn^�]����Ă��܂������C���̓���123�n�����ꂵ�Ă����悤�Ŗ{�q�lH408�Ґ�����T�n103-282���O�����ʐ^��3�����[������Ă��܂����B��[���u��WAU102�^��3����ڂ��Ă��܂��B��O�̃N�n103-545�́C���l���k����103�n���ɍۂ��N���n103�`�ƂƂ��ɓo�ꂵ�����������̐���ԂŁC�O�ʂ̃W�����p���ȗ����ꂷ�����肵�Ă���̂������ł��B (2017/07/17�lj��@2023/04/07�V���h�[����) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.212-21 1991�N4��6�� ��~�m 18�Ґ� �N�n103-624�� 4�� ��ΐ��@�����C�݁����钬 |
�Ί�/�� �N���n103-137+���n102-298+�T�n103-232+�N�n103-624 ��� ��ΐ����X�V�F��103�n4���ʼn^�]�������s�������u���݂����v�C�擪�̓N�n103�`500�ԑ�ԁB (2022/06/09�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �N�n103-1201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.254-36 1992�N1��19�� ���}�g 31�Ґ� �N�n103-1201�� 5�� ���c�� ���H���������� |
���c/�� �N�n103-1201+���n103-1201+���n102-1201+���n103-1203+�N���n102-1201
�䑷�q 103�n1200�ԑ�͉c�c�n���S������������p�ɐ������ꂽ�ԑ�敪�ŁC�O�ʊђʌ`�̓����͐��c���p��1000�ԑ�ԂƓ��l�ł���WS-ATC�𓋍ڂ��Ă���C���������ɃN���n102��z�u����6M1T��7���Ŋ��܂�����1991�N����2�Ґ���4M1T�Ɍ��Ԃ����։���/���c���̕t���Ґ��ɓ]�p����܂����B�擪�Ԃ̃N�n103-1201�͔j�b�g���ŗ����C1202�ȍ~�̓��j�b�g���ƂȂ�������1���ْ݂̂̈[�ԂƂȂ��Ă��܂��B��[���u�͊e�ԂƂ�AU712�`2��ځC��[�d���̓��n102��160kVA��MG�𓋍ڂ��Ă��܂��B���̕Ґ��̍Ō�����N���n102-1201�ł��B (2023/05/19�lj�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �N�n103 1501-1518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.N8305-34 1983�N3��10�� E03�E04�Ґ� �N�n103-1503�� 6�� ���^�] �}����@���� |
������/�� E03 �N�n103-1503+���n103-1503+���n102-1503 +���n103-1504+���n102-1504+�N�n103-1504 E04 ���� ���ÂɂĎ��^�]����103�n1500�ԑ�ԁB6���ђʕҐ��ł����O��3�����ŕҐ��ԍ����������Ă��܂��B�Ȃ��C�}����͐����Õ���������Ƃ��Ă���C�t�H�ƂȂ�܂����C���E�傪�k���ɂ��邱�Ƃ��l����Η��ɂ��Ȃ��Ă���Ǝv���܂��B (2020/09/27�lj��@2023/04/10�F����m�C�Y�) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.N8307-09 1983�N3��15�� E01�E02�Ґ� 103�n1500�ԑ� 6�� ���^�] �}����@���z�� |
������/�� E01 �N�n103-1501+���n103-1501+���n102-1501 +���n103-1502+���n102-1502+�N�n103-1502 E02 ���� �d��������s��ʋǏ������O�Ɏ��^�]���s��103�n1500�ԑ�B��s�}�s�u��������v�ɏ�荇�킹���t�@���̕����玎�^�]���������������B�e�ł��܂����B (2019/01/27�lj��@2023/04/10�F���) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �N���n103 3501-3509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_120526-6 2012�N5��26�� BH5�Ґ� �N���n103-3505�� 2�� �d�A���@�P�H |
���O/�� �N���n103-3505+�N���n102-3505 �P�H �d�A���P�H-���O�Ԃɓ�������Ă���103�n3500�ԑ��BH5�Ґ��B��O�����O���ŃN���n103-3505�C��낪�N���n102-3505�ł��B �i2023/04/08���C�h��) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �N���n102 3501-3509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_120526-6 2012�N5��26�� BH4�Ґ� �N���n102-3504�� 4�� �d�A���@�P�H |
���O/�� �N���n103+�N���n102+�N���n103-3504+�N���n102-3504 �P�H �P�H�ɓ��������S���B���������ɂȂ�܂����B��O�̓N���n102-3504�ł��B �i2023/04/08���C�h��) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�@2013�N1��14���@�y�[�W�쐬�J�n �@2013�N1��20���@�y�[�W�V�� �@2023�N3��16���@�L���v�V���������E���֊��� �@2023�N4��6���@101�n�̃y�[�W��V�݂����� �@2023�N4��6���@Safari�Ŕ��p�����d�b�ԍ������N�����̂��� �@2023�N4��8���@�ʐ^���C�h������ �@2023�N4��11���@�V���Ԉꗗ�\��lj� �@2023�N4��12���@�����ԕ\��lj� �@2023�N4��12���@���n������`�����ɕ��בւ� �@2023�N4��12���@�V���Ԉꗗ�\����щ����ԕ\����e�ʐ^�ւ̃����N��ݒu �@2023�N4��16���@�Ґ��\�̍�����������ɓ��� ���Q�l���� �@���� ���@�@�V�`���d�̂���݁@�S���t�@��241�@1981�N5�����@��F�� �@�W�F�[��A�[����A�[�� JR�d�ԕҐ��\ '92�~�� 1992�N1��1�� �@Wikipedia�@���S103�n�d�� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
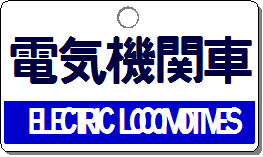 |
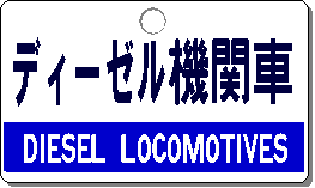 |
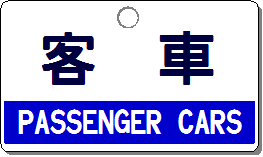 |
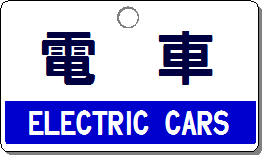 |
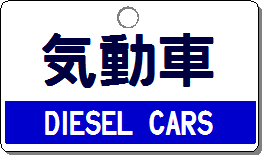 |
 |
|---|